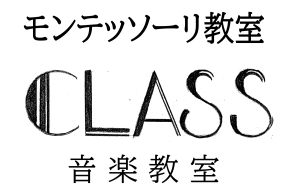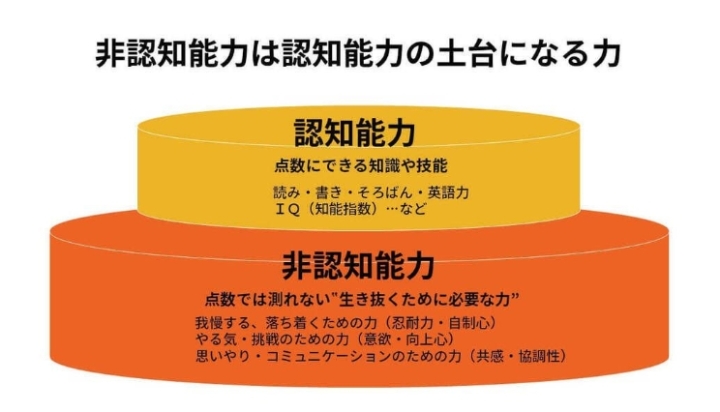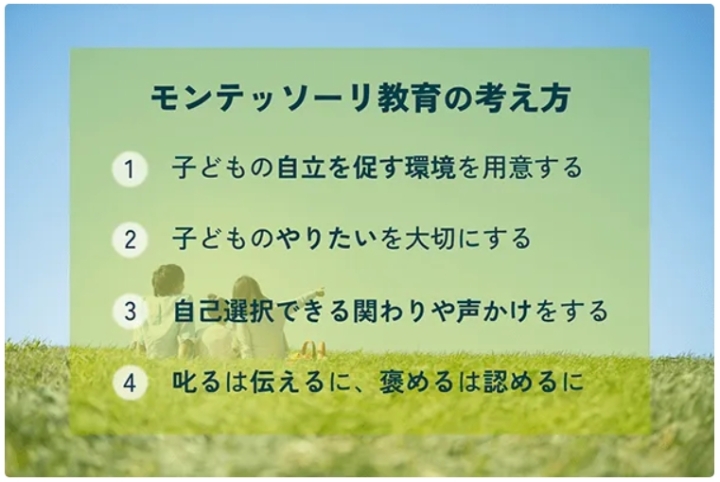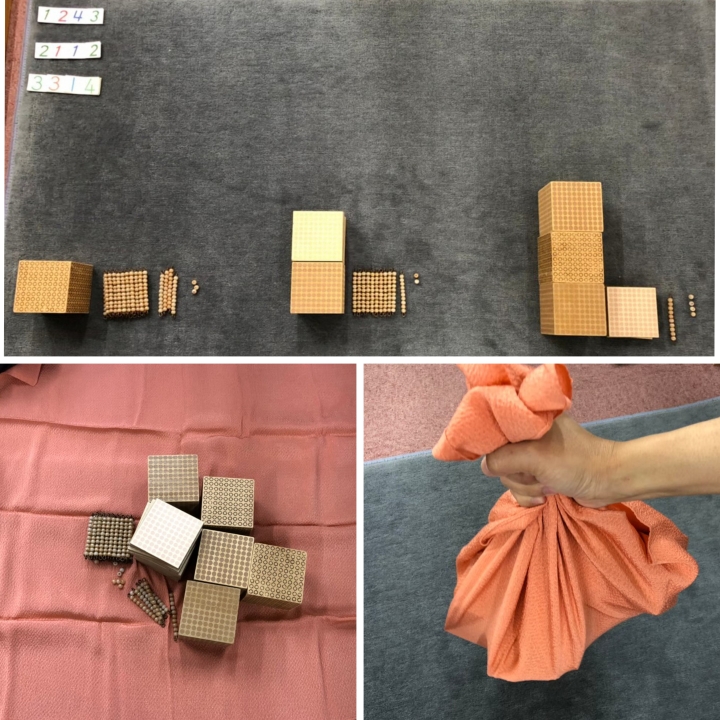こんなに重要!非認知能力
モンテッソーリ教育を受けた人たちには、みなさんが知っている方々がたくさんいらっしゃいます。
・藤井聡太(将棋棋士)
・ジェフ・ベゾス(Amazon創業者)
・ラリーペイジ&セルゲイ・ブリン(Google創業者)
・アンネ・フランク(アンネの日記)
などなど
みなさん自分の好きなことに集中し、探求し、その能力を伸ばしたのですね。
すご過ぎてウチの子には関係ない?!
本当にそうでしょうか?
音楽講師時代、保育士時代と、
「この子にじっくりと集中する時間と場所が提供できたら、どんなに伸びていくだろう…」
と何度も思いました。
目の前のお子さんは、本当にそんな能力を持っていないと言えますか?
もしも素晴らしい能力を秘めていたらどうでしょう?
****************
非認知能力という言葉を聞いたことがあるかたも多いと思います。
認知能力(記憶力、計算力、読解力など目に見える能力)と違って数値化しにくい能力です。目標達成への意欲、やりきる力、自制心、協調性、コミュニケーション能力などと表現されています。
認知能力と非認知能力の違いとは? 人生に役立つ力
非認知能力には大きく分けて、
「自分に対する能力」と
「社会や人に対する能力」があります。
****************
「自分に対する能力」
・自己肯定感
自分はこのままでいいんだ!と自分を認める力
・好奇心・発想
新しいことへ興味を持ち、工夫しながら考える力
・主体性
自分で目標を立て行動する力
・やりきる力
困難に直面しても諦めずに努力できる力
・自制心
感情・衝動などを自分でコントロールする力
****************
「社会や人に対する能力」
・コミュニケーション能力
自分の考えや気持ちを相手に伝え、相手の考えや気持ちも理解しようとする力
・協調性
他社と協力し、目標を達成する力
・共感力
相手の立場に立って考える思いやりの力
****************
モンテッソーリ教育では子どもの活動をおしごとと呼びます。
大人が仕事をするように、子どもが自分自身を作り上げるための大切な活動だからです。
おしごとは教師が決めて子どもにやらせるのではありません。子ども自身が自分で今日やりたいおしごとを選び、やり切ったと思えるまで、何度も何度も繰り返します。
少し難しい場面でも挑戦を繰り返し
自分でやりきる力
そんな子どもたちを見守りながら育てていくのが
モンテッソーリ教育です。
今まさに注目されている
非認知能力を伸ばす教育です。
モンテッソーリ教育は生きていくうえで必要な「非認知能力」を伸ばすための教育【話題の子育てキーワード解説】
少し専門的な “非認知能力と認知能力”